Gleamはif/else文・式やreturnといった構文を持たないので,caseとパターンマッチングのみで条件分岐を表現し,関数の最後の式で評価された値を返り値とする.なかなかに思想が強い.
例として,何かしらのIDをバリデーションしたい場面があったとする.
IDの形式はID-XXXX(Xは数字)とし,成功したらIDの数字部分をパースしたものを,失敗したらフォーマットが不正というエラーを返すような形にする.
仮にcaseだけを使って書くとしたら,このような見た目になる.
const id_prefix = "ID-"
fn validate_id(str: String) -> Result(Int, String) {
case str |> string.startswith(id_prefix) {
True -> {
case str |> string.replace(id_prefix, "") |> int.parse {
Ok(value) -> Ok(value)
Error(_) -> Error("IDの数字部をパース出来ませんでした")
}
}
False -> Error("IDの形式が不正です")
}
}
pub fn main() {
validate_id("ID-1234")
|> io.debug
validate_id("ID-ABCD")
|> io.debug
validate_id("1234")
|> io.debug
}
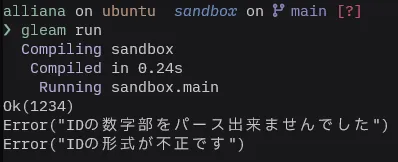
これでも動くことには動くが,今後IDに桁数の制約やその他の条件が増えたりした場合,caseがどんどんネストしていき,コードが絶望的に見にくくなるだろう.

それと,6行目のOk(value) -> Ok(value)もなんだか冗長な気がする.というか正しい値を返す文は分岐の真ん中ではなく,一番最後に置きたい(これは思想の問題かもしれないが).
こうなるとEarly-returnしたくなる.が,Gleamにはifもelseもreturnもないのである!
どうしたものか…と悩んでいたところ,bool.guardという関数があることを知った.
GleamのTips#66685d444293a40000d73ba3
gleam/bool · gleam_stdlib · v0.40.0
Run a callback function if the given bool is
False, otherwise return a default value.With a
useexpression this function can simulate the early-return pattern found in some other programming languages.
関数の説明にもearly-returnと記述がある.読み進めると
In a procedural language:
if (predicate) return value; // ...In Gleam with a
useexpression:use <- guard(when: predicate, return: value) // ...
とあり,一般的な手続き型言語におけるEarly-returnのように使えるようだ.
早速これで最初の例を書き換えてみる.
fn validate_id(str: String) -> Result(Int, String) {
use <- bool.guard(
str |> string.starts_with(id_prefix) |> bool.negate,
Error("IDの形式が不正です")
)
use id_num <- result.try(
str
|> string.replace(id_prefix, "")
|> int.parse
|> result.replace_error(
"IDの数字部をパース出来ませんでした"
),
)
Ok(id_num)
}
若干の書き換えはあったものの,最初の例と比べて,
- インデントが浅くなった
- エラーを最初に蹴ることで関数の一番最後に正しい値を持ってこれた
ことによりコードの見通しが良くなった.
めでたしめでたし.
…なぜこんなことが出来たのか?use周りの理解が浅かったのでいろいろと調査した.
use式より後ろに書かれたコードはuseで展開した関数(ここではgleeting())のコールバック関数(name: fn() → String)の中に渡される.
fn gleeting(name: fn() -> String) -> Nil {
let message = "Hello " <> name() <> "!"
io.println(message)
}
pub fn main() {
use <- gleeting()
"Gleam"
}
このとき,use <- gleeting()より後ろに書かれた”Gleam”という文字列は単なる文字列としてではなく,fn () { “Gleam” }という無名関数になり,gleeting関数のname引数にコールバック関数として渡される.
また,useは式なので,useで展開した関数のコールバックはブロックに囲むことで変数に束縛したり,囲まずにそのままにして関数の返り値とすることもできる.
fn gleeting(name: fn() -> String) -> String {
"Hello " <> name() <> "!"
}
pub fn main() {
let message = {
use <- gleeting()
"Gleam"
}
io.println(message)
}
ここでは,上の例のgleeting関数の返り値をNilからStringにし,そのコールバックを変数に束縛している.
さて,bool.guardに話を戻す.bool.guardはこのように定義されている.
pub fn guard(
when requirement: Bool,
return consequence: t,
otherwise alternative: fn() -> t,
) -> t {
case requirement {
True -> consequence
False -> alternative()
}
}
when(requirement)が
- Trueの時にはコールバックは実行されず,
return(consequence)引数に渡された値を - Falseの時にはコールバック(
otherwise())を実行しその返り値を
それぞれ返す.
Trueの時にコールバックを実行しないで値を返すことで,Early-returnを実現しているということだった.
敢えてuseを使わずに同じ動作をするコードを書いた場合,このような見た目になる.
bool.guard(
when: str |> string.starts_with(id_prefix) |> bool.negate,
return: Error("IDの形式が不正です"),
otherwise: fn() {
result.try(
str
|> string.replace(id_prefix, "")
|> int.parse
|> result.replace_error(
"IDの数字部をパース出来ませんでした"
),
apply: fn(id_num) { Ok(id_num) },
)
}
)
useを使うことで,コールバックに渡している処理をネストすることなく書ける,というカラクリだった.
だいぶ寄り道した感があったが,Gleamへの理解がより深まった.